
はじめに
エパデールSは、閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍や疼痛、冷えの改善や、高脂血症に用いられる薬です。
日本全国広く、使われている薬ですので、使ったことのある患者さんもいるのではないでしょうか?
今回は、エパデールSについて説明していきたいと思います。
目次
エパデールSってどんな薬?
エパデールSってどうやって効くの?
エパデールSの用法・用量
エパデールSの副作用・注意点
エパデールS開発の歴史
まとめ
エパデールってどんな薬?
エパデールSは1999年1月に発売が開始されたEPA製剤です。
EPAとは、イコサペンタエン酸エチルの略で、閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善及び、高脂血症の治療薬として用いられています。
日本では、300mgと600mgが1999年1月に、900mgが2004年7月に販売開始されました。
効能・効果
閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善
高脂血症
引用:エパデールS 添付文書
エパデールSってどうやって効くの?
高脂血症に関して、エパデールSはトリグリセリド(TG)高値および総コレステロール(TC)高値の高脂血症に効果があります。
肝臓に取り込まれたエパデールSは、脂肪酸の合成を抑制し、また分解を促進することで、TG・TCの消費を促し・生成を抑え、動脈硬化の原因となる血清コレステロール値を下げる働きをします。
細かいところを説明すると、脂質合成系の酵素の働きを促進させる働きをしているSREBP-1cという遺伝子の転写を抑制することによりTGの合成を抑制、PPARαの活性を上げることにより、β酸化を促しTG・TSの消費を多くし、血清コレステロール値を下げます。
その他にも、血小板膜リン脂質に取り込まれることで、血小板凝集を抑制し、血液が固まりにくくする効果や血管壁に取り込まれて、動脈の弾力性維持に寄与したりします。
効果効能の【閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善】は、血小板凝集の抑制が寄与していると考えられています。
エパデールSの用法・用量
用法及び用量
●閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、 疼痛及び冷感の改善 イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回600mgを1日3回、 毎食直後に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。●高脂血症 イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回900mgを1日2回 又は1回600mgを1日3回、食直後に経口投与する。 ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回900mg、1日3回まで増量できる。
引用:エパデールS インタビューフォーム
この薬は食直後に服用となっています。
なんででしょうか??
食直後のほうが吸収量が増えるからです。
食事をすることで、少なからず胃や腸に脂肪分の多い物質がたまります。
その結果、脂溶性のエパデールSがそれらと一緒に体に吸収されることで、効率よく吸収されるので、食直後に服用することとなっています。
ちなみに、食直後とは食事後10分以内に服用することを言います。
閉塞性動脈硬化症に対しては1日3回、1回600mgを服用。
高脂血症は、1日2回もしくは1回、1回900mg服用、もしくは1日3回、1回600mg服用することとあります。
ただし、症状によっては増加することもあるので、医師の指示通りの服用を心がけてください。
エパデールSの副作用・注意点
副作用としては、悪心・下痢・嘔吐・腹痛・胸やけといった消化器症状や、発疹・掻痒感といった過敏症が多く報告されています。
他にも副作用はあるので、服用していて体調の違和感を感じたら医師に相談するようにしましょう。
エパデールS開発の歴史
エパデールSの有効成分である、イコサペントサン(エイコサペンタエン酸・EPA)は、どうして発見されたのでしょうか。
1970年代、グリーンランド人が血栓性疾患の罹患率が低いことと、血清コレステロール値も低値であることが判明しました。
どうしてだろうかと調査を進めると、食事で海棲哺乳類(クジラ・アザラシ・アシカなど海に生息する哺乳類)を多く摂取しており、それらにはEPAが豊富に含まれていることがわかりました。
そこで、EPAを製剤化して臨床研究を行ったところ、閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善や高脂血症の改善に効果があると判明したという背景があります。
まとめ
エパデールSは、閉塞性動脈硬化症による潰瘍、疼痛及び冷感の改善や、高脂血症(特にTG高値)の治療薬です。
1日1~3回服用する薬で、症状に応じて用法用量が変わるので、医師の指示通り服用するようにしましょう。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






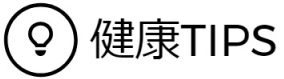
この記事へのコメントはありません。